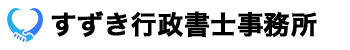遺言書で争いを未然に防止する

民法では、相続人ごとに、遺産を相続できる割合が決まっています。
例えば、相続人が妻と子ども2人の場合は、妻が2分の1、子ども4分の1ずつ分けることになります。相続財産がすべて現金や預貯金の場合は、すんなりと分けられるので問題ありませんが、相続財産が不動産のみの場合など、平等に分けるのが難しいケースもあります。遺産分割協議において、各相続人が自分の取り分を主張し(相続人の配偶者などが口出しすることが多い)、更に、過去の生前贈与などを持ち出してくると、もう収拾がつかなくなります。仲のよかった家族が骨肉の争いをする、みなさんも相続争いの話の1つや2つは聞かれたことがあるのではないでしょうか。
大切な家族に争ってほしくない! 円満に相続させたい!
遺言書を書いて、だれに相続させるのかを決めておくことで、相続争いを防ぐことができます。
ただ、残念ながら遺言書は法的文書です。書き方が間違っていると、遺言書が原因で相続争いになることもあります。
そのような事態を避けるためには、専門家のサポートが必要です。
すずき行政書士事務所は、大切な財産を大切な方へ確実に承継させるお手伝いをさせていただきます。
主な遺言書の種類と特徴
よく書かれているのは、公正証書遺言と自筆証書遺言の2つです。
公正証書遺言
メリット
・全国の公証役場で公証人が作成するため、法的なトラブルがほとんどなく証拠能力が高い
・相続発生後、すぐに手続きが可能
デメリット
・証人二人が必要
・費用がかかる
・公証役場の敷居が高い
自筆証書遺言(法務局の遺言書預かり制度を利用した場合)
政府がオンラインTVで、自筆証書遺言保管制度を広報しています。わかりやすいのでぜひご覧ください。
メリット
・どこでも書ける
・費用が安くすむ
デメリット
・だれにもチェックされないので、書き方に不備があると無効になるおそれがある
・相続発生後、法務局で「遺言書情報証明書」の交付請求が必要
あんしん相談所では、遺言者様のご希望に沿って、公正証書遺言、自筆証書遺言の作成サポートを行っております。
まずは、公正証書遺言サポートからご説明させていただきます。
公正証書遺言作成サポート

上記の通り、公正証書遺言は全国の公証役場で作成します。公証人という法律のプロ(元裁判官や元検事など)が作成するため、証拠能力は非常に高いです。費用がかかる、証人二人が必要というデメリットはありますが、現時点では一番お勧めの遺言書です。
1.遺言書の原案作成
遺言者様から徹底した聞き取り調査を行い、ご希望に沿った遺言書を作成します。
法的に問題はないか、相続争いの原因になる可能性はないかなどを検討します。
2.相続税対策(ご希望の方)
相続税がかかる場合、ご希望により生前贈与などの対策を考えます。税理士と連携して行います。
3.公証役場との打ち合わせ
遺言内容の確認、作成日時の予約、証人の用意など、すべてあんしん相談所が行います。
4.アフターサービス
定期的なご連絡を行い、遺言内容の変更などに迅速に対応します。
公正証書遺言作成サポートの流れ
-
- 1.ご相談
- まずはお気軽のお問い合わせください。
-
- 2.受任
- 正式受任。
-
- 3.遺言書の原案を作成

-
①相続人、受遺者の確認
相続人、受遺者を戸籍謄本等を取得し確認します。
②財産目録の作成
どのような財産があるのかを一覧表にまとめます。
財産を証明する書類として、不動産登記事項証明書、固定資産税評価証明書、預貯金口座の情報、証券会社の取引残高報告書などをご用意いただきます。③遺言書の原案を作成
遺言者様から徹底した聞き取り調査を行い、ご希望に沿った遺言書を作成します。
法的に問題はないか、相続争いの原因になる可能性はないかなどを検討します。
-
- 4.公証役場との打ち合わせ
- 公証人と遺言内容について打ち合わせ、証人の準備、作成日時の予約を行います。
-
- 5.公証役場で遺言書作成

- 作成当日、遺言書は既に出来上がっています。公証人が遺言書を読み上げ、内容を確認し、遺言者様と証人二人が署名・押印して終了となります。
遺言書の原本は、公証役場で保管され、正本と謄本を持ち帰ります。
-
- 6.公証役場手数料支払い
- 公証役場への手数料については、こちらをご覧ください。
-
- 7.報酬
- 公証役場への手数料とは別に、行政書士への報酬が発生します。
-
- 8.遺言書の保管
- 遺言書の原本は公証役場で保管され、遺言者は、正本と謄本を持ち帰ります。内容は同じものですが、相続手続きを行うには正本が必要になります。遺言者が両方保管しておいてもよいですが、正本は遺言執行者、あるいは相続人の一人に渡しておいてもよいでしょう。(遺言書を渡すことでトラブルにならないかをよく考えてからにしてください)紛失した場合でも、原本は公証役場で保管されているので安心です。
-
- 9.アフターサービス
- 公正証書遺言を作成いただいたお客様には、定期的に連絡をとらせていただいております。財産関係の変化や自分の気持ちの変化で、遺言書を書き替えたいという場合にも、迅速に対応させていただきます。末永くおつきあいさせていただきたいと思っています。
自筆証書遺言作成サポート

自筆証書遺言は、自分で書く遺言書です。
従来は、自筆証書遺言のデメリットとして、紛失、改ざん、隠匿や発見されないおそれなどがあり、家庭裁判所の検認手続き(自筆証書遺言の様式を満たしているかをチェックする)も必要でした。
令和2年7月10日以降、法務局での「自筆証書遺言保管制度」が始まり、これらのデメリットが解消されることになりました。
ただし、法務局は遺言内容をチェックしません。法務局もこの点については注意喚起されています。
家族のためを思って書いた遺言書なのに、争いの原因になってしまったのでは元も子もありません。
自筆証書遺言作成サポートをご利用いただくと、
遺言者様から徹底した聞き取り調査を行い、ご希望に沿った遺言書を作成します。
法的に問題はないか、相続争いの原因になる可能性はないかなどを検討します。
遺言者様の大切な財産を大切な方へ確実に承継させることができます。
自筆証書遺言作成サポートをご利用のお客様のご感想
「息子に遺言書を書いてほしいと言われ、息子が鱸先生を探してきてくれました。自分で遺言書を書くといっても、意味がわからず、先生にお願いして本当によかったです。手が震えて、なかなか思うように進みませんでしたが、先生が励ましてくれて、「頑張ろう」という気持ちになりました。保管申請当日も、付き添っていただけたので安心できました。本当にありがとうございました。」80代男性
鱸より
手が震えて思うように書けないなかで、何度も練習していただき、ありがとうございました。無事に保管申請できて何よりです。ご家族皆様にも喜んでいただき、とてもうれしく思っています。
法務局での遺言書保管制度
遺言書の保管の申請
・遺言者は、法務局の遺言書保管官に対し、自筆証書遺言の保管の申請やその撤回ができます。
・遺言書の閲覧ができます。
「遺言書情報証明書」の請求等
・遺言者の死亡後、相続人等は、「遺言書情報証明書」の交付請求ができます。また、遺言書の閲覧をすることができます。
・遺言書保管官は、1人の相続人等が「遺言書情報証明書」の交付請求をしたときには他の相続人等に遺言書を保管している旨を通知します。
遺言書の検認手続きの不要
家庭裁判所の検認手続きなしで、遺言執行ができます。
費用
・保管申請 1件につき、3,900円
・遺言書の閲覧請求(モニター) 1回につき1,400円
・遺言書の閲覧請求(原本) 1回につき1,400円
・遺言書情報証明書の交付請求 1通につき1,400円
自筆証書遺言作成サポートの流れ
-
- 1.ご相談
- まずはお気軽にお問い合わせください。
-
- 2.受任
- 正式受任。
-
- 3.遺言書の原案を作成

-
①相続人、受遺者の確認
相続人、受遺者を戸籍謄本等を取得し確認します。
②財産目録の作成
どのような財産があるのかを一覧表にまとめます。
財産を証明する書類として、不動産登記事項証明書、固定資産税評価証明書、預貯金口座の情報、証券会社の取引残高報告書などをご用意いただきます③遺言書の原案を作成
遺言者様から徹底した聞き取り調査を行い、ご希望に沿った遺言書を作成します。
法的に問題はないか、相続争いの原因になる可能性はないかなどを検討します。
-
- 4.ご自身で遺言書を作成していただきます
- 原案を確認していただき、よければ、ご自身で遺言書を書いていただきます。
- あんしん相談所が原案を作成しますので、遺言者様は迷うことなく遺言書を書くことができます。

-
- 5.行政書士への報酬
- 行政書士への報酬をお支払いいただきます。
-
- 6.遺言書の保管
- 令和2年7月10日から始まる法務局の遺言書保管制度を、是非、ご利用ください。
-
- 7.アフターサービス
- 定期的に連絡をとらせていただきます。財産関係の変化や自分の気持ちの変化で、遺言書を書き替えたいという場合にも、迅速に対応させていただきます。末永くおつきあいさせていただきたいと思っています。
→ 自筆証書遺言について相談する
よくあるご質問
自筆証書遺言について
筆記用具は決まっていますか?
特に決まりはありません。ボールペン、マジック、万年筆など。鉛筆は故意に消されるおそれもあるので避けるのがよいでしょう。
用紙は決まっていますか?
特に決まりはありません。便箋、コピー用紙など。劣化するものは避けるとよいでしょう。
法務省のHPから遺言書の様式をダウンロードできます。
縦書き、横書き、文字数の制限はありますか?
特にありません。用紙の余白の制限はありますので、上記法務省の様式を参考にしてください。
タイトルは決まっていますか?
タイトルがなくても法律上の問題はありませんが、「遺言書」としておくと、相続人がわかりやすいでしょう。
印鑑は実印でしょうか?
認印でも問題ありませんが、実印が望ましいでしょう。
すべて手書きですか?
いいえ、本文、日付、署名は手書きですが、別紙として添付する場合に限り、財産目録をパソコンで作成したり、コピーを添付することができます。もちろん、すべてを手書きしてかまいません。
本文の書き方は決まっていますか?
特に決まりはありません。
日付は、元号、西暦、どちらでもよいですか?
はい、かまいません。ただし、令和2年5月吉日などは、日にちが特定できませんので無効になります。
自分のことは何と書けばよいですか?
特に決まりはありません。「私は」でも、「遺言者は」でも、「お父さんは」などでもかまいません。
相続人のことは何と書けばよいですか?
妻の姓名、長男の姓名、長女の姓名 ・・・を書けばよいです。性が同じ場合は、名前だけでもよいと思いますが、結婚して性が変わっている場合は、姓名を書かれるのがよいでしょう。
銀行預金はどんなふうに書けばよいですか?
○○銀行 ○○支店 口座番号○○○○〇○○ のすべての預金を○○○○に相続させる。
口座番号はなしでもOKです。
もしくは、別紙、財産目録として、通帳のコピー(銀行名、支店名、口座番号、氏名が記載されているページ)を添付します。添付した場合、そのページには、遺言者の署名・押印が必要です。
不動産はどんなふうに書けばよいですか?
法務局で登記事項証明書を取得し、その通り記載します。もしくは、登記事項証明書を別紙、財産目録として添付します。添付した場合、そのページには、遺言者の署名・押印が必要です。
録音や録画で遺言を残すことはできますか?
できません。書面に残す必要があります。
書き間違った場合はどうすればよいですか?
訂正場所を示して、変更したことを付記します。そのうえで、署名し、かつ変更場所に印を押す必要があります。
できれば、書き直したほうがよいでしょう。
作成後の保管方法は?
法務局の遺言書保管制度をご利用ください。法務局が自筆証書遺言を預かってくれます。
同じ内容の遺言書は何通作成してもよいのですか?
はい、同じものを複数作成してもかまいません。法務局に預けたものと同じものを複数作成して、各相続人に渡しておいてもよいでしょう。
自筆証書遺言のデメリットは何ですか?
遺言内容をだれにもチェックされないことと、相続発生後、遺言執行するために、「遺言書情報証明書」を法務局に請求することです。
公正証書遺言について
公正証書遺言は、どこで作れますか?
全国の公証役場で作ることができます。
公証役場に行けば、その場で作成できるのですか?
公証人との事前の打ち合わせが必要になります。
公証役場に行かずに公正証書を作成する方法はありますか?
ありません。あんしん相談所にご依頼いただければ、公証役場との打ち合わせは、あんしん相談所が行います。遺言者様は、一度だけ公証役場に行くだけで遺言書が作成できます。
公正証書遺言のメリットは何ですか?
・遺言書が、様式の不備によって無効になることはありません。
・遺言書は公証役場で保管されるので、紛失、改ざん、隠匿のおそれがありません。
・遺言者の死亡後、全国の公証役場で遺言の検索ができます。
・相続発生後すぐに、遺言が執行できます。
公正証書遺言のデメリットは何ですか?
費用がかかってしまうことと、作成時に証人が二人必要になりますので、遺言書の内容を完全に秘密にすることはできません。
費用はどれくらいかかりますか?
公証役場の手数料は、こちらから その他、行政書士に依頼する場合は、別途費用が必要です。
公正証書遺言を作り直したいのですが。
新しい遺言書を作成する必要があります。遺言書は、日付の新しいものが優先されます。公正証書遺言を自筆証書遺言で取り消すことも可能です。
遺言書に書いた財産を処分することはできますか?
はい、可能です。遺言書に書かれている財産が、相続開始時に存在しない場合は、その部分は記載されていなかったものとして扱われます。ただし、財産の内容が大きく変わった場合は、相続争いの原因になりかねませんので、遺言書の書き換えをお勧めします。
遺言執行者とは何ですか?
遺言執行者は、遺言の内容を実現するために手続きを行う人のことです。未成年者と破産者以外はなることができます。相続人や受遺者などの利害関係人を指定することもできますが、遺言執行者が過度なストレスを感じたり、手続きがスムーズにいかないケースもあります。法律知識のある専門家を指定するのも一つの手でしょう。
遺言と異なる遺産分割をすることは可能ですか?
相続人全員の同意があれば可能です。遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者の同意も必要でしょう。