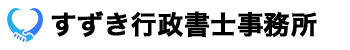配偶者居住権ー相続後、妻が自宅を追い出されそうになったときに使える権利
配偶者居住権とは
配偶者居住権は、被相続人(故人)が亡くなった後も、配偶者が引き続き自宅に住み続けられる権利のことです。
例えば、夫が亡くなり、相続人が妻と長男だったとします。
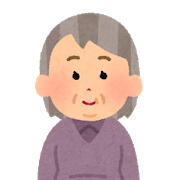

相続財産は、自宅不動産3,000万円 と預貯金1,000万円


法定相続分通りに分けると、妻と長男は、それぞれ2,000万円ずつ相続します。
優しい長男が妻の老後を心配して、「お母さんが、家も預貯金も全部相続していいよ。」と言ってくれれば万々歳!
妻は、自宅不動産と預貯金全部を相続することができ、安心して老後の生活を送ることができます。
ここで、配偶者居住権が問題になることはありません。
が、
妻が長男から「僕には、法定相続分の2,000万円相続する権利があるから、お母さんは家を売ってお金を支払って」と言われたら、妻は、「私には配偶者居住権があるから、自宅に住み続けることができるの。」と長男に主張することができます。
配偶者居住権は、配偶者の老後生活の保護を目的として作られた権利です。タイトルのように、配偶者が自宅を追い出されそうになったときに使える権利と理解するとわかりやすいと思います。
配偶者居住権の成立要件
1.相続開始時に被相続人の所有する建物に居住していたこと
2.相続開始時に被相続人が配偶者以外の者と建物を共有していないこと
夫と妻の共有名義の場合、配偶者居住権は設定できますが、夫と他の相続人の共有名義や第三者との共有名義の場合、配偶者居住権は設定できません。
3.以下のいずれかに該当
①遺産分割により配偶者居住権を取得するものとされたこと
相続人全員が配偶者居住権を設定することに同意しなければなりません。例えば、長男が、妻の配偶者居住権を認めず遺産分割が成立しない場合、妻は家庭裁判所に調停を申し立て、そこで配偶者居住権が認められるか判断されることになります。
②配偶者居住権が遺贈の目的とされたこと
遺言書で、配偶者居住権を配偶者に「遺贈する」と書いているとき
通常、相続人の場合、「相続させる」と書きますが、「相続させる」と書くと、配偶者がそれを望まない場合、相続放棄するほかないことになり、配偶者の利益を害する恐れがあるため、「遺贈する」と書くそうです。遺贈は、望まない場合、それを拒否することができます。
注意!配偶者居住権は、法律上の配偶者にのみ認められる権利で、内縁の妻(夫)には認められていません。内縁の妻(夫)に自宅を遺したい場合、遺言書を書いておくか、生前贈与しておくようにしてください。
配偶者居住権は所有権のなかの「住む権利」
所有権には、物を使用する権利(住む権利)と収益する権利(売却益)があります。
配偶者居住権は、所有権のなかの「住む権利」だけを配偶者に与えるものです。賃貸物件のようなイメージでしょうか。
収益する権利は、他の相続人(上記の例の場合は長男)が取得することになります。
配偶者居住権の期間は、配偶者が死亡するまで、あるいは、10年、20年と任意に決めることが可能です。
配偶者居住権は、配偶者が死亡すれば消滅し、相続の対象にはまりません。
配偶者居住権を主張するためには登記が必要
配偶者居住権は、建物にのみ認められている権利です。そして、この権利を主張するためには、登記を行う必要があります。
登記しない場合、長男に勝手に売却されてしまう恐れもでてきます。
配偶者居住権のデメリット
配偶者居住権は、配偶者の「住む権利」を守ってくれますが、デメリットもあります。
1.配偶者居住権は売却できません。例えば、配偶者が介護施設に入るために売却したいと思っても、配偶者居住権を設定したままの状態では売却できません。他の相続人との合意解除後、売却できますが、配偶者から他の相続人への贈与とみなされ贈与税が課せられます。
2.配偶者は、建物の固定資産税や日常の修繕費用を支払います。大規模な修繕(例えば、台風で半壊したなど)は、他の相続人の負担になります。また、土地の固定資産税は、他の相続人が支払うことになり、他の相続人からすると、使用もできない土地の固定資産税を支払わなければならず、不満の要因となります。
(話し合いで配偶者が支払うことも可能だと思います)
相続税のかかる人は、配偶者居住権を設定すると節税になる?
相続税のかかる人は、配偶者居住権を設定すると相続税が節税になるケースがあるようです。すべてというわけではないそうなので、税理士さんに相談してください。
配偶者居住権は、令和2年(2020年)4月1日から施行されていますが、まだまだ、実例が少ないです。
配偶者居住権の評価をどうするのかなど、一般の方にはわかりにくい内容となっていますので、ご利用の際は、専門家にご相談ください。